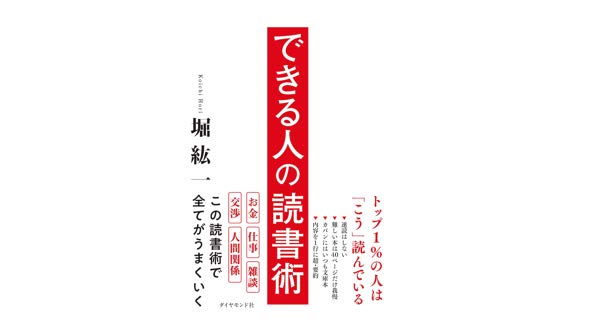「できる人の読書術」の書評です。
ポイントだけサラッとまとめてみたので参考にしてみてください。原著を読むとより理解が深まると思いますのでぜひ読んでみてくださいね。
堀 紘一さんとは?

堀紘一さんはこんな人でした。ザ・エリートですね。
- 東大法学部卒
- 読売新聞社
- 三菱商事
- ハーバード大学にてMBA取得
- ボストンコンサルティング社長
- ドリームインキュベータを起業
- 同社を東証一部上場企業へ
教養を身に付けて一流の人間になる
「教養を身に付けて一流の人間になる」のがこれからの生き方。AIの台頭などで変化の激しい世の中では2流の人間は生き残れない。
一流の人間になるにはどうしたらいいかというと「読書」をするのがベスト。
インターネットよりも読書に価値がある
読書などせずに、ネットで調べればいいのでは?→インターネット全盛の時代だからこそ、良質な情報である「読書」に価値がある。
インターネットに頼らない工夫をしてみることも重要。
哲学を学んで洞察力をみにつける
どんな職業であっても哲学を学んでおくとよい。AIは膨大なデータから「〜してはいけない」というのは答えをだすのは得意だが、未来思考で「〜すればいい」という最適解を出すのは苦手。
哲学を学んで得た洞察力というのはこれからのAI社会できっと活きてくる。
読書はディープラーニング
グーグルの親会社アルファベットがつくった「アルファ碁」は圧倒的な自己対局で人間の能力を超えた。しかしながら、人間にとっての読書もある意味ディープラーニングである。
耳学問と読書
耳学問というのは人から話をきくこと。教養を身につけるには耳学問と読書という方法があるが、耳学問は敷居がたかい(人的ネットワークが必要)
一方、読書はいつでもどこでもできるので活用しない理由はない。つまり、読書なら誰でも教養を深めて一流の人間に近づける。
年間50冊の読書は続けたい
サラリーマンは忙しいが、年間50冊〜100冊の読書は続けたいところ。忙しくとも「スキマ時間」を活用して読み進めるのがおすすめ。
掘さん自身も年100冊以上の読書をしているが、ほとんどは「スキマ時間」を利用している。
読書の仕方
一流の読書の仕方はこちら。一行に超要約は難しい・・
- 速読はしない
- 難しい本も40ページだけ我慢
- カバンにはいつも文庫本
- 内容を一行に超要約
まとめ
この本を読んで感じたことはこちらです。読書をつづけながら、哲学書にふれるいいきっかけをもらった気がします。哲学学びましょう!
- 情報は量よりも質
- 読書は続けていく価値がある
- 未来のために哲学を学ぼう